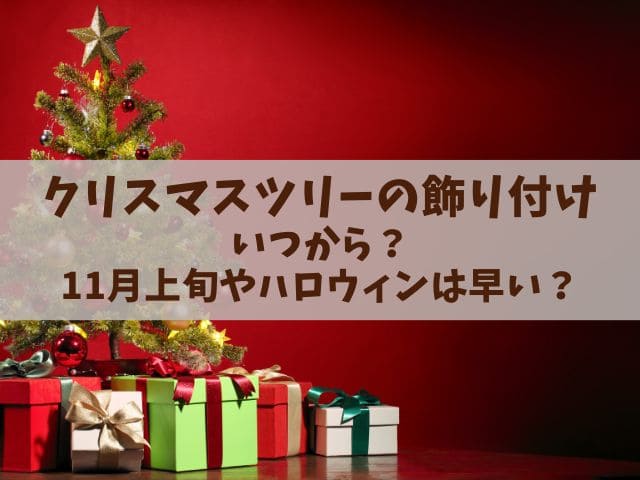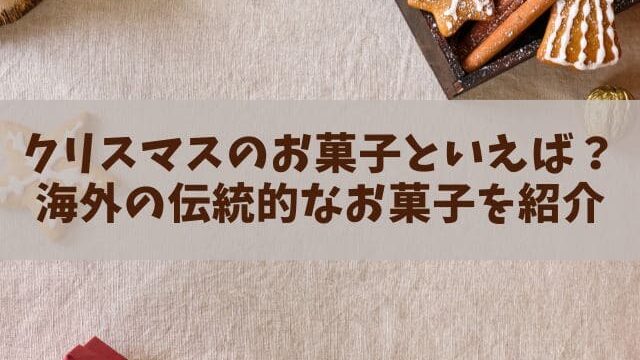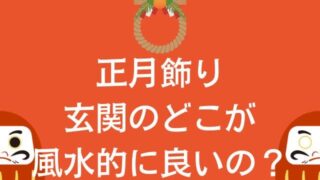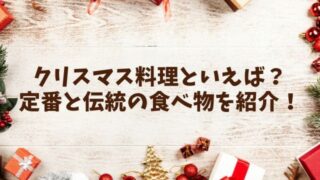冬の楽しいイベントといえば、クリスマス♪
クリスマスと聞いて、何を思いうかべますか?
わたしがクリスマスに向けてはじめに準備するのは、クリスマスツリーです。
そんなときに気になるのが「いつからクリスマスツリーを飾るのか?」ということ。
そこでこの記事では、
- クリスマスツリーはいつから飾れるのか?
- どんなものを飾るのか?
- オーナメントの意味は?
などクリスマスツリーに関する疑問について詳しく調べてみましたので、ご紹介します!
クリスマスツリー飾り付けはいつから?

クリスマスの雰囲気をいちはやく演出する、日本のデパートなどお店の飾りつけは、11月初旬から中旬にクリスマスモードになることが多いです。
一般家庭では、11月下旬から12月上旬に飾りつけをすることが多いです。
この時期に飾ると、1か月ほどクリスマスツリーを楽しむことができます。せっかく飾りつけをするなら、長くクリスマスツリーを楽しみたいですよね。
キリスト教の文化をもつ欧米では、11月最後の日曜日に飾ることが多いです。2021年でいうと、【11月28日】です。
キリスト教には、「アドベント」と呼ばれるクリスマスを迎える準備の期間があります。「アドベント」はクリスマスの4週間前の日曜日から、クリスマス当日までをさします。
家族がそろう休日の日曜日に、みんなでクリスマスツリーを飾って、お祝いの準備を楽しむようです。
クリスマスツリー飾り付け11月上旬や10月ハロウィンは早すぎる?
クリスマスの飾り付けは、一般的にクリスマスの直前の日曜日から遡って4週間前からと言われていますが、11月上旬から飾る家庭もあります!
最近では、クリスマスの1ヶ月間だけではせっかくのツリーがもったいないということで、ハロウィンの飾り付けをして10月から飾る家庭や施設もあるんです。
今年もハロウィンツリーが登場しましたよ
🎃👻
potteちゃんもツリーの前でちょこんとお待ちしてます🐻🐻★彡#はこだて明治館#はこだて明治館ハロウィンツリー#ハロウィン#はこだて明治館オリジナルくまのpotte#ぬい撮り#フォトスポット#函館#teddybear pic.twitter.com/FsBxLks1C1— はこだて明治館【公式】 (@meijikan) September 7, 2023
せっかく買ったなら、長く楽しむのもいいですね♪
クリスマスツリーはいつ片付けるの?

欧米では、12月25日のクリスマスを過ぎた後も、クリスマスツリーが飾られていることが多いそうです。
というのも、欧米では日本のお正月のように、新年を迎えるための飾りや準備というものはないため、クリスマスの飾りが続くようです。
キリスト教の文化としては、1月6日ごろまで飾り、クリスマスのイベントは終了ということですが、一般家庭では片付ける時期はあまり気にされていないようです。
日本では、クリスマスが終わると一気にお正月モードに突入しますね。
新しい年を迎えるための準備があるので、12月26日には西洋風のクリスマスツリーは片付けて、和風なお正月の飾りを準備しはじめる家庭が多いのではないでしょうか。
日本のひな人形などは、行事が終わったあとも飾っておくとよくないと言われることがありますが、クリスマスの飾りについては、特にそのようなことはないようです。
意外と知らない!クリスマスツリーオーナメントの意味

ここからは意外と知らないクリスマスツリーに飾られているオーナメントの意味についてご紹介します。
クリスマスツリーの起源
クリスマスツリーといえば、もみの木をイメージすることが多いと思います。
地域にもよりますが、常緑樹である針葉樹に飾りつけを楽しみます。冬でも枯れず、常に緑色をした木なので、「永遠の象徴」とされています。
クリスマスツリーの起源は、様々な言い伝えがあり、はっきりとはわかっておりません。
諸説ありますが、ヨーロッパの原住民ゲルマン民族が木を信仰していたことがはじまりと言われています。
ゲルマン民族が「ユール」と呼ばれる冬至のお祭りのときに神の力が宿るとして大切にしていたカシの木が、のちのクリスマスツリーになっていったようです。
18世紀には、現在のようにデコレーションをして飾っていました。
トップスター
イエス・キリストが誕生したとき、それを知らせるために特別な星が現れました。
この星を「ベツレヘムの星」といいます。クリスマスツリーの頂上の星は、このベツレヘムの星を表しています。
ベツレヘムの星を見てキリストの誕生を悟った三人の博士たちは、この星をたよりにして出かけます。
そして無事にベツレヘムにたどり着いた博士たちは、宝物を捧げ、イエス・キリストを拝みます。
天使
クリスマスの飾りに天使が使われるのは、天使が神様の使者としてイエス・キリスト誕生のお話に登場するからです。
聖母マリアへイエス・キリストが誕生することを伝えたのは天使・ガブリエルでした。ガブリエルは「あなたのおなかの中に神様の子どもがいます。
その子をイエスと名付けなさい」と知らせ、マリアがこれを受け入れることでイエス・キリストは誕生しました。
ベル
イエス・キリストが生まれたとき、天使がその喜びをベルの音で表した、と言われています。現代でも結婚式などのお祝い事でベルを鳴らすことがありますね。
クリスマスにはよくハンドベルの演奏が行われますが、それも天使のベルの音がもとになっています。
また、ベルには魔除けの意味もあるそうです。
りんごとオーナメントボール
クリスマスツリーにはさまざまな色のボールが飾られます。
オーナメントボールはもともとりんごを飾っていました。りんごが不作になってしまったときに、代わりにガラス玉を飾ったことがオーナメントボールのはじまりだそうです。
りんごは旧約聖書に登場する、アダムとイブが「食べてはいけない」と言われたのに食べてしまった「知恵の木の実」を表しています。
キャンディケイン
ストライプでかわいいキャンディの飾りは、キャンディケインといいます。ケインとは杖のことで、キャンディケインは杖の形をしています。
これは羊飼いが持っている、羊を導く杖を表しているそうです。
聖書では、イエス・キリストは羊飼いに、わたしたち人は羊に例えられ、イエス・キリストは人々を導く存在とされています。
靴下
靴下が飾られるようになったのは、聖ニコラウスという、サンタクロースのモデルになった人のお話がもとになっています。
貧しい家の子どものためにと、家に金貨を投げ入れ、それが偶然暖炉のそばの靴下に入ったというお話から、「クリスマスの夜に靴下を置いておくと、プレゼントを入れてくれる」という言い伝えになり、靴下が飾られるようになりました。
リース
リースの円の形は永遠を象徴しています。「人々の愛と命が永遠に続きますように」という願いがこめられています。
ヒイラギ
イエス・キリストが十字架にはりつけになる前に、いばらの冠を頭にかぶせられました。
とげとげしているひいらぎの葉は、いばらの冠を表しています。
ひいらぎの中央についている赤い実は、イエス・キリストの血を表していると言われています。
綿
ツリーやリースに使われる綿は、降り積もる雪を表しています。
飾りつけるとふわふわとしていて、本当に雪が乗っているかのように見えます。
イルミネーション
昔は、クリスマスツリーに星を表すためろうそくを灯していたそうです。火を使うろうそくは火事の原因となるため、クリスマスツリーの足元にはいつも消火のための水を用意していていました。
火事の心配を解消するために広まったのが、電気を使ったイルミネーションでした。
電気の普及、小型化に合わせてクリスマスのイルミネーションも進化していきました。
リボン
クリスマスツリーやリース結ばれているリボンは「人々が永遠の絆で結ばれますように」という願いがこめられています。
また、夢の実現や努力の成果といった意味もあるとされています。
松ぼっくり
昔から松の木、松ぼっくりは、不老長寿や豊穣を象徴するものとして大切にされてきました。リースなどに飾られる松ぼっくりも豊穣、つまり農作物が豊かに実り、生活に困りませんようにという願いがこめられています。
また、松ぼっくりはもみの木の実を象徴しているという説もあります。
聖母マリアとその許嫁のヨゼフがエジプトへ逃げるときに、もみの実がふたりの身を隠し、安全に逃げることを手伝ったという言い伝えから、もみの実よりも手に入りやすい松ぼっくりが飾られるようになった、という話もあります。
まとめ
何気なく飾り付けていたクリスマスツリーですが、一つひとつに意味や願いが込められていたのですね。
キリスト教をはじめとする、さまざまな文化やお話がもとになって、現在のクリスマスの形になったことがわかりました。
華やかなクリスマスツリー、飾ることが今年も楽しみです。
みなさんも、家族や友だちと一緒に、クリスマスを楽しく過ごせるといいですね♪
▼こちらの記事もどうぞ▼
クリスマスといえば何?定番の食べ物アメリカや世界のメニューも紹介!
クリスマスのお菓子といえば?ドイツなど世界の伝統スイーツを紹介!