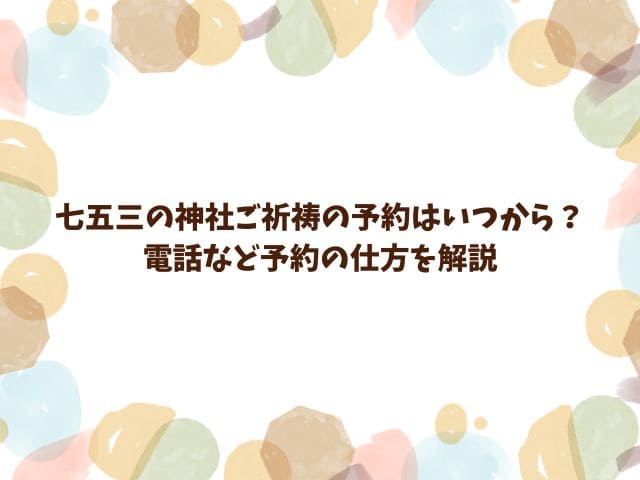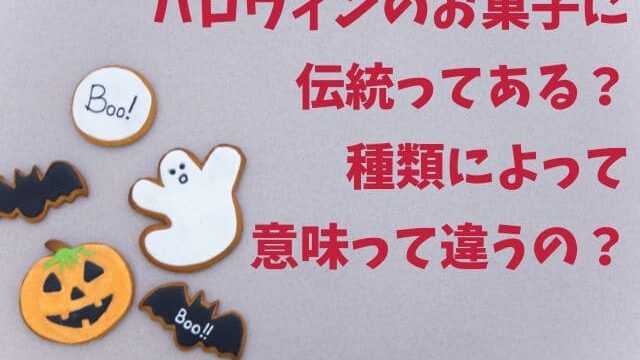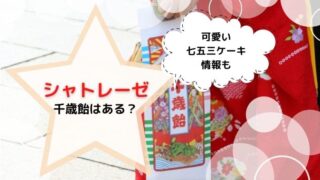お子さんの七五三、そろそろ準備を始めようかなって考えているところでしょうか。
神社の予約っていつから始まるんだろう、予約なしでも大丈夫なのかな、って気になりますよね。
実は七五三の予約開始時期は神社によってバラバラで、早いところだと3月から受付が始まるんです。
この記事を読めば、2025年の七五三に向けた予約のベストタイミングや、スムーズにお祝いする方法がわかりますよ。
11月の大安や友引は本当にすぐ埋まってしまうので、早めの行動が大切なんです。
この記事では、予約方法から当日の流れ、さらには最近のトレンドまで、ママ目線でわかりやすくお伝えしていきますね。
七五三の神社予約の基本知識
まずは七五三の予約を考える前に、七五三という行事そのものについて確認しておきましょう。
意味を理解すると、予約の必要性や準備の大切さもより実感できるはずです。
七五三のご祈祷の意味
七五三は、お子さんが無事に成長したことを神さまやご先祖さまに感謝して、これからの健やかな成長をお祈りする大切な行事なんです。
昔は病気や栄養不足で小さな子どもが亡くなることが多かったから。
だから7歳まで無事に育ったことを、本当に喜んでお祝いしていたんですね。
現代では医療も発達して、子どもが元気に育つのが当たり前になりましたよね。
でもだからこそ、改めて健康に感謝して、これからの成長を願う気持ちを大切にしたいものです。
神社でのご祈祷は、家族みんなでお子さんの成長を実感できる特別な時間になりますよ。
男の子と女の子でお祝いする年齢
七五三は年齢によってお祝いするタイミングが決まっています。
男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いするのが一般的なんですね。
ただし、これは絶対的なルールではないんです。
地域によっては男の子は5歳だけお祝いするところもありますし、兄弟姉妹がいる場合は一緒にお祝いすることも多いんです。
数え年でお祝いするか満年齢でお祝いするかも、各ご家庭の考え方次第になります。
最近は満年齢でお祝いするご家庭が増えてきていますね。
一番大切なのは、家族みんなが揃える日を選ぶことなんですよ。
2025年の七五三予約開始時期
七五三の予約がいつから始まるのか、これが一番知りたいポイントですよね。
神社によって違いはあるものの、最新の傾向を押さえておけば予約のタイミングを逃すことはありません。
ここでは2025年の最新情報をお伝えしますね。
神社別の予約開始時期
七五三の予約受付は、神社によって本当にバラバラです。
私が調べたところ、早いところでは3月頃から予約を受け付けている神社もありました。
多くの神社では、9月や10月から予約を開始するところが多いですね。
でも人気の大きな神社では、それよりもっと早く予約が埋まってしまうこともあるんです。
予約方法も神社によって違っていて、電話予約のみのところもあれば、最近ではWEBから予約できる神社も増えてきたんです。
まずは参拝したい神社の公式サイトをチェックするか、電話で問い合わせてみるのがおすすめですよ。
予約開始日を逃さないように、早めに確認しておきましょう。
2025年11月の大安・友引カレンダー
縁起の良い日にお祝いしたいと考えるご家庭も多いですよね。
2025年11月の大安と友引の日をご紹介しますね。
- 4日(火)
- 10日(月)
- 16日(日)
- 21日(金)
- 27日(木)
- 1日(土)
- 7日(金)
- 13日(木)
- 19日(水)
- 24日(月・祝)
特に16日(日)の大安と、24日(月・祝)の友引は三連休最終日でもあるので、かなりの混雑が予想されます。
六曜を気にしないご家庭も増えていますが、おじいちゃんおばあちゃんの世代は気にされることも多いんです。
家族みんなが気持ちよくお祝いできる日を選びたいですね。
平日の大安なら比較的空いている可能性が高いので、お仕事の調整ができるなら狙い目かもしれません。
早期予約のメリット
「まだ半年も先だし、そんなに急がなくても…」って思うかもしれませんが、実は早めの予約には大きなメリットがあるんです。
まず、希望の日時を確実に押さえられます。
11月の土日祝日、特に大安や友引はあっという間に埋まってしまいます。
着物のレンタルも早めに予約すれば、人気の柄やデザインから選べるんです。
直前だと「この柄はもう予約済みです」って言われることも少なくないんですよね。
それに、フォトスタジオでは早期予約割引やキャンペーンを実施していることも多いんです。
写真データがもらえたり、特典がついたりするのでお得なんですよ。
何より、早めに予定を立てておけば、当日まで余裕を持って準備できるので安心ですよね。
神社予約の具体的な方法
予約のタイミングがわかったら、次は実際の予約方法です。
最近は電話だけでなくWEB予約も増えてきましたが、それぞれにメリットがあるんですよ。
予約時に確認すべきポイントも合わせて見ていきましょう。
電話予約とWEB予約の違い
最近は神社でもWEB予約システムを導入するところが増えてきたんです。
スマホから24時間いつでも予約できるので便利ですよね。
WEB予約のメリットは、リアルタイムで空き状況が確認できることなんです。
仕事の合間や家事の合間にサッと予約できるのも助かりますよね。
一方で電話予約なら、わからないことをその場で質問できるのが良いところなんです。
「子どもがまだ小さいんですけど、待ち時間はどのくらいですか?」とか「車椅子の祖母も一緒なんですが」といった相談もできますよね。
個人的には、まずWEBで空き状況をチェックして、質問があれば電話で確認するという方法がおすすめです。
ただし神社によっては電話予約のみ、または予約不要というところもあります。
事前に確認しておくことが大切ですね。
予約時の確認事項
予約の電話をする時、何を聞けばいいか迷いますよね。
これだけは確認しておきたいポイントをまとめてみました。
1. ご祈祷の開始時間と所要時間 当日のスケジュールを立てるために、何時から始まって何分くらいかかるのか聞いておきましょう。
2. 初穂料の金額 お金のことは聞きにくいかもしれませんが、当日慌てないためにも確認しておくと安心です。相場は5,000円から10,000円くらいのところが多いですよ。
3. 参加人数の制限 コロナ以降、人数制限を設けている神社もあります。祖父母も一緒の場合は特に確認しておきましょう。
4. 写真撮影のルール ご祈祷中の撮影が可能かどうか、境内での撮影に制限はないかを聞いておくといいですね。
5. 駐車場の有無と混雑状況 車で行く予定なら、駐車場の台数や混雑する時間帯も教えてもらえることがあります。
これらを確認しておけば、当日スムーズに進められますよ。
人気神社の予約状況
都市部の有名神社では、予約開始と同時にどんどん埋まっていくんです。
実際の例を見てみましょう。
東京の明治神宮では、7月1日に予約を開始するのですが、11月の土日祝日は2〜3日で埋まってしまうことも珍しくないんです。
地元の小さな神社でも、11月15日前後の大安・友引は早々に予約でいっぱいになります。
「まだ2ヶ月も先だから大丈夫」と思っていたら、もう予約が取れなかったという声もよく聞くんです。
逆に平日、特に午後の時間帯は比較的予約が取りやすい傾向にあります。
お仕事の都合がつくなら、平日の午後を狙ってみるのも一つの手ですよ。
それから、9月や10月にお参りするという選択肢もあります。
「11月じゃないとダメ」ということはないので、混雑を避けたい方は時期をずらすのもおすすめですね。
予約なしで参拝する場合の注意点
予約を受け付けていない神社も実は多いんです。
当日受付にはメリットもデメリットもあるので、事前に理解しておくことが大切ですよ。
特に混雑する時間帯を知っておくと、待ち時間を減らせます。
当日受付のメリットとデメリット
予約を受け付けていない神社も実は多いんです。
当日受付にはメリットもデメリットもあるので、しっかり理解しておきましょう。
当日受付のメリットは、予定が変わりやすい小さなお子さんがいるご家庭には、予約不要は助かりますよね。
「当日の子どもの機嫌次第で決められる」というのは大きなメリットなんです。
急な体調不良でキャンセルの心配をしなくていいのも安心ですね。
当日受付のデメリットとして、一番のデメリットは待ち時間なんです。
受付順にご祈祷を行うので、到着が遅いと何時間も待つことになることもあるんですよ。
3歳や5歳のお子さんにとって、慣れない着物で長時間待つのはかなりの負担になります。
機嫌が悪くなって、せっかくの記念撮影で泣いちゃった…なんてことも。
それに、あまりに遅い時間に到着すると、その日のご祈祷が終了してしまって受け付けてもらえない可能性もあるんです。
混雑を避けるための時間帯
当日受付の神社に行く場合、時間帯選びがとても大切なんです。
私の経験と周りのママ友の話をまとめると、こんな感じです。
朝一番(開門直後)が最もおすすめ。社が開く時間に合わせて到着すれば、待ち時間をかなり短縮できますよ。
9時開門なら8時45分には到着しているくらいがいいですね。
朝早いのは大変ですが、子どももまだ元気なので、ご機嫌でご祈祷を受けられる可能性が高いんです。
午後の遅めの時間も狙い目。意外かもしれませんが、15時以降も比較的空いていることが多いんです。お昼過ぎのピークが過ぎた頃なんですね。
ただし、ご祈祷の受付終了時間には注意が必要ですよ。
16時や17時で受付終了する神社も多いので、余裕を持って到着しましょう。
避けたい時間帯は、10時〜14時頃は最も混雑します。
特に11時前後は「お昼前に終わらせたい」と考える方が集中するんですよね。
土日祝日の大安・友引は、どの時間帯も混んでいると覚悟しておいた方がいいかもしれません。
待ち時間対策グッズ
万が一待ち時間が長くなってしまった時のために、準備しておくと安心なグッズがあるんです。
- 絵本や小さなおもちゃ(音が出ないもの)
- ウェットティッシュと除菌スプレー
- 飲み物とおやつ(こぼれにくいもの)
- 着物の予備の足袋や草履
- 簡易的な座布団やブランケット
境内のベンチや待合室で過ごすことを考えて、座りやすいものがあると助かりますよ。
それから、事前に境内の様子を下見しておくのもおすすめです。
お手洗いの場所や、子どもが少し遊べるスペースがないか確認しておくと安心ですね。
待ち時間も「神社探検」として楽しめるように工夫してみてください。
お子さんにとっては全てが新鮮な体験になるはずですよ。
初穂料の準備と包み方
ご祈祷を受ける際には、初穂料という謝礼をお納めするのが一般的です。
金額の相場や正しい包み方を知っておけば、当日慌てることもありません。
マナーをしっかり押さえておきましょう。
初穂料の相場
初穂料って聞き慣れない言葉ですよね。これは神社へのお礼として納めるお金のことなんです。
相場は神社によって違うんですが、一般的には5,000円から10,000円くらいのところが多いですよ。
中には金額を明示している神社もあれば、「お気持ちで」という神社もあるんです。
金額が明示されていない場合は、予約の時に「初穂料はいくらくらいお納めすればよろしいでしょうか?」と聞いてしまうのが一番確実です。
お金のことを聞くのは気が引けるかもしれませんが、神社の方も慣れていますから大丈夫ですよ。
一般的に、金額が高いとご祈祷の内容が変わる(お札が大きくなる、お土産が豪華になるなど)ことがあります。
でも、お子さんへの祝福の気持ちは金額に関係なく同じですからね。
ちなみに、兄弟姉妹で一緒にご祈祷を受ける場合は、お子さん一人ずつに初穂料が必要になることが多いので確認しておきましょう。
のし袋の選び方と書き方
初穂料はのし袋に入れて納めるんです。どんなのし袋を選べばいいか、ちょっと迷いますよね。
のし袋の選び方 水引は「蝶結び」のものを選んでください。紅白の蝶結びが一般的ですよ。結び切りではないので注意してくださいね。
最近はかわいいデザインののし袋も増えているんです。七五三らしい華やかなデザインを選ぶのも素敵ですね。
表書きの書き方 のし袋の上段(水引の上)には「初穂料」または「御初穂料」と書きます。「玉串料」でも構いません。
下段(水引の下)には、お子さんのお名前をフルネームで書きましょう。
兄弟姉妹で一緒の場合は、連名で書くこともできます。
筆ペンか毛筆で、濃い黒で書くのがマナーです。薄墨は使わないでくださいね。
中袋には金額を書きます。
「金 伍仟円」「金 壱萬円」というように、旧字体で書くのが正式ですが、普通の数字でも大丈夫ですよ。
当日の渡し方
初穂料の渡し方にもちょっとしたマナーがあるんです。知っておくとスマートですよ。
受付でご祈祷を申し込む際に、のし袋のまま両手で渡します。
「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えるといいですね。
のし袋から出してお金だけ渡すことはしないでください。必ずのし袋に入れたまま渡しましょう。
もし袱紗(ふくさ)に包んで持ってきた場合は、受付で袱紗から出してから渡します。
袱紗ごと渡すことはないので注意してくださいね。
それから、お釣りが出ないように準備しておくのがマナーです。事前に銀行やコンビニで新札を用意しておくといいですよ。

当日の持ち物と服装
予約も済んで初穂料も準備できたら、あとは当日の準備です。
何を持っていけばいいのか、親の服装はどうすればいいのか、意外と悩むポイントが多いんですよね。
チェックリストとして活用してください。
必須の持ち物リスト
当日になって「あれがない!」と慌てないように、必要なものをリストアップしておきますね。
絶対に必要なもの
- 初穂料(のし袋に入れて)
- カメラやスマホ(充電満タンで!)
- ハンカチ・ティッシュ
- お子さんの着替え一式
- 履きなれた靴(行き帰り用)
特に着替えは大事なんです。慣れない着物で汚してしまったり、機嫌が悪くなったりすることもありますからね。
それから、予約確認のメールや電話番号をスマホに保存しておくのも忘れずに。万が一遅刻しそうな時にすぐ連絡できますよ。
あると便利な持ち物
必須ではないけれど、持っていくと安心なものもご紹介しますね。
あると助かるもの
- 絆創膏(草履で靴擦れすることも)
- 髪留めやピンの予備
- 扇子やハンカチタオル(暑い時期なら)
- 予備のストッキング(ママ用)
- 簡単な裁縫セット(着物のほつれ対応)
- おやつと飲み物
- 小さなおもちゃ(待ち時間用)
- モバイルバッテリー
荷物は増えますが、「持ってきてよかった!」となることが多いんですよ。
着物のレンタルなら、オンラインで完結するサービスが便利なんですよ。私の周りでも、家にいながら好きな着物を選べると評判なんです。着付けに必要な小物も全部セットになっているので、初めてのママでも安心して準備できますね。
親の服装マナー
お子さんの服装は決まったけど、親は何を着ればいいの?って悩みますよね。
ママの服装 訪問着や色無地、付け下げなどの着物が格式高くて素敵です。でも洋装でも全然問題ないんですよ。
洋装なら、ワンピースやスーツがおすすめです。色は落ち着いた色合いで、スカート丈は膝が隠れるくらいが上品ですね。
主役はお子さんなので、親が派手すぎないように気をつけましょう。でも地味すぎるのも寂しいので、アクセサリーや小物で華やかさをプラスするといいですよ。
パパの服装 スーツが無難で間違いないです。ビジネススーツでもフォーマルスーツでも大丈夫ですよ。
ネクタイは明るめの色を選ぶと、お祝いの場にふさわしい華やかさが出ます。白やシルバー、淡いブルーなんかがいいですね。
靴は革靴で、しっかり磨いておきましょう。スニーカーやサンダルはNGです。

写真撮影の選択肢
七五三の大切な思い出を残す写真撮影。
スタジオで撮るか、出張撮影を依頼するか、それぞれの特徴を理解して選びましょう。
最近のトレンドも押さえておくと、より満足度の高い写真が残せますよ。
スタジオ撮影と出張撮影の比較
写真撮影をどうするか、これも大きな悩みどころですよね。最近は選択肢が増えて、それぞれに良さがあるんです。
スタジオ撮影のメリット 照明や背景がプロ仕様で整っているので、確実にきれいな写真が撮れるんです。天候に左右されないのも安心ですね。
着物レンタルとセットになっているプランも多くて、コスパが良いことも。早期予約割引を使えばさらにお得になりますよ。
ただし、スタジオの雰囲気に緊張してしまうお子さんもいます。それに少し「作られた感」のある写真になることもありますね。
出張撮影のメリット 神社の境内や自然の中で撮影できるので、その場の雰囲気が伝わる自然な表情が残せるんです。お子さんもリラックスしやすいですよね。
最近人気なのが、プロのカメラマンに来てもらう出張撮影なんです。
神社での自然な表情を撮ってもらえるので、スタジオとはまた違った素敵な写真が残せますよ。
料金も思ったよりリーズナブルで、1万円台から利用できるサービスもあるんです。
デメリットは天候に左右されることと、撮影可能な神社とそうでない神社があることですね。事前に確認が必要です。
出張撮影サービスの選び方
出張撮影サービスを選ぶ時のポイントをお伝えしますね。
選ぶ時のチェックポイント
- 料金体系が明確か(追加料金の有無)
- データは何枚もらえるか
- カメラマンの実績と作風
- キャンセルポリシー
- 撮影時間の長さ
口コミやサンプル写真をしっかり見て、自分の好みに合うカメラマンを選ぶのが大切です。
人気の出張撮影サービスには、専用のマッチングサイトもあるんですよ。カメラマンのプロフィールや作品を見比べられるので便利ですね。
予約は早めがおすすめです。人気のカメラマンは数ヶ月前から埋まってしまうこともあるので注意してください。
SNS映えする写真のコツ
せっかくだからSNSに投稿したい!というママも多いですよね。映える写真のちょっとしたコツをお教えします。
構図のポイント 鳥居や本殿を背景に入れると、七五三らしさが出ます。
でも建物を入れすぎると圧迫感が出るので、バランスが大事なんです。
お子さんの目線は少し上を向いてもらうと、表情が明るく見えます。
無理に笑顔を作らせるより、自然な表情の方が素敵な写真になりますよ。
タイミングの取り方 朝早めの時間帯は光が柔らかくて、ふんわりした雰囲気の写真が撮れるんです。午後の強い日差しより断然おすすめですよ。
お子さんが千歳飴を持っている瞬間や、家族で手をつないでいる後ろ姿なんかも、後で見返した時に「あの時はこうだったな」って思い出せる大切な1枚になりますね。
多様化する七五三のスタイル
時代とともに七五三のお祝い方法も変化してきました。
必ずしも伝統的なスタイルにこだわる必要はないんです。それぞれのご家庭に合った、無理のないお祝いの形を見つけていきましょう。
神社参拝以外のお祝い方法
最近は七五三のお祝いの形も本当に多様化してきたんですよ。必ずしも神社に行かなくちゃいけないわけではないんです。
お寺での七五三 神社だけでなく、お寺でも七五三のご祈祷を受け付けているところがあるんです。特に檀家さんなら、親しみのあるお寺でお祝いするのも素敵ですよね。
自宅でのお祝い 神社には行かずに、自宅で記念撮影とお祝い会食だけするご家庭も増えています。祖父母を呼んでゆっくりお祝いできるのがいいですね。
フォトスタジオでの撮影のみ ご祈祷は省略して、フォトスタジオでの記念撮影を中心にするという選択肢もあるんです。仕事が忙しくてスケジュール調整が難しい場合には、こういう方法もありなんですよ。
大切なのは、お子さんの成長を家族でお祝いする気持ちなんです。形式にとらわれすぎず、各ご家庭に合った方法を選んでくださいね。
柔軟な日程調整のすすめ
「11月15日に神社でご祈祷をして…」という伝統的なスタイルにこだわらなくても大丈夫なんですよ。
時期をずらすメリット 9月や10月にお参りすれば混雑を避けられますし、写真撮影の予約も取りやすいんです。お子さんもまだ暑さに慣れているので、着物を着るのが楽かもしれませんね。
逆に12月や1月にずらすという方もいるんですよ。年末年始で親戚が集まるタイミングに合わせられるという利点があります。
参拝と撮影を分ける 11月に神社参拝をして、写真撮影は前撮りで5月や6月に済ませておく。これなら両方ゆっくり楽しめますよね。
当日は参拝だけに集中できるので、お子さんの負担も減らせるんです。
兄弟姉妹でまとめてお祝い 年齢が近い兄弟姉妹がいる場合、一緒にお祝いするご家庭も多いんです。上の子が7歳、下の子が3歳というタイミングで、2人まとめて七五三をするんですね。
家族みんなで何度もスケジュール調整するのは大変ですから、合理的な選択だと思います。
よくある質問
ここまで読んでいただいて、まだ気になることがあるかもしれませんね。多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。参考にしてみてください。
Q1. 七五三の予約は何ヶ月前からするべきですか?
A. 理想は3〜6ヶ月前です。特に11月の土日祝日、大安・友引を希望する場合は、早ければ早いほど確実ですよ。遅くとも2ヶ月前には予約を完了させておきましょう。
Q2. 予約なしで神社に行って、受け付けてもらえなかったらどうしますか?
A. 事前に電話で確認することをおすすめします。当日の受付終了時間や、予約が必要かどうかは神社によって違うんです。確認してから行けば、そういった心配はなくなりますよ。
Q3. 雨が降ったらどうすればいいですか?
A. ご祈祷自体は屋内で行うので、雨でも大丈夫です。ただし写真撮影を予定している場合は、日程変更を検討してもいいかもしれませんね。予約時にキャンセルポリシーを確認しておくと安心です。
Q4. 子どもが体調を崩した場合、キャンセル料はかかりますか?
A. 神社のご祈祷自体にキャンセル料がかかることはほとんどありません。ただし写真スタジオや着物レンタルは、キャンセル料が発生することがあります。予約時に必ず確認しておきましょう。
Q5. 祖父母も一緒に参加しますが、人数制限はありますか?
A. コロナ以降、人数制限を設けている神社もあります。予約時に参加人数を伝えて、確認しておくことをおすすめします。待合スペースの広さも神社によって違いますからね。
Q6. 初穂料は新札でないとダメですか?
A. 必ずしも新札である必要はありませんが、できれば新札を用意するのがマナーです。折り目やシワのないきれいなお札を準備しておきましょう。
Q7. 写真撮影とご祈祷、どちらを先にするべきですか?
A. 一般的にはご祈祷を先にするケースが多いです。着崩れる前に神様にご挨拶をして、その後ゆっくり写真撮影という流れがスムーズですよ。
ただし、お子さんの年齢や性格によっては、先に写真を撮ってしまう方がいい場合もあります。
まとめ
七五三の神社予約について、たくさんお伝えしてきましたが、一番大切なポイントをまとめますね。
まず、予約の開始時期は神社によって違いますが、早いところでは3月から受付が始まります。
11月の土日祝日、特に大安や友引は本当にすぐ埋まってしまうので、早めの行動が肝心なんですよ。
予約方法も電話やWEBなど選択肢が増えてきました。自分に合った方法で、確実に予約を押さえましょう。
予約時には初穂料の金額や撮影ルール、駐車場の有無も忘れずに確認してくださいね。
当日の持ち物や服装も事前にしっかり準備しておけば、安心してお祝いの日を迎えられます。
特に初穂料をのし袋に入れておくことと、お子さんの着替えを用意することは忘れないでください。
最近は七五三のスタイルも多様化していて、神社参拝だけが正解ではないんです。
家族の都合に合わせて、無理のない形でお祝いするのが一番ですよね。
大切なのは、お子さんの健やかな成長を家族みんなで喜び、感謝する気持ちです。
予約や準備は早めに済ませて、当日は思い出に残る素敵な一日にしてくださいね。
みなさんの七五三が、笑顔あふれる素晴らしいお祝いになりますように!