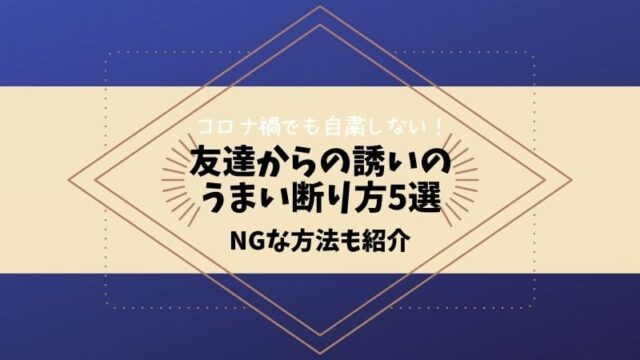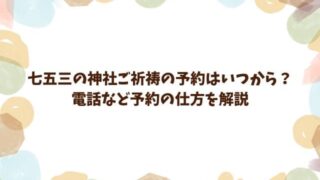お宮参りや七五三で神社に行くとき、「初穂料ってそのまま渡していいの?」って不安になりますよね。
私も初めての時は、のし袋に入れるだけでいいのか、それともふくさっていう布に包まないとダメなのか、本当に分からなくて困ったんです。
この記事では、初穂料を「そのまま」渡すことについての疑問から、正しいマナー、ふくさがない時の対処法まで、2025年最新の情報をまとめてお伝えします。
初めての方でも安心して準備できるように、分かりやすく解説していきますよ。
この記事を読めば、初穂料の渡し方で失敗することなく、心を込めて神様にお供えができるようになりますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
初穂料を「そのまま」渡すってどういうこと?
まず、「そのまま」という言葉には2つの意味があるんです。
一つ目は「のし袋に入れずにそのまま現金で」、二つ目は「ふくさに包まずにそのまま」という意味なんですね。
どちらの疑問もよく聞かれるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
「のし袋に入れずそのまま現金」はマナー違反なの
結論から言うと、初穂料は神社でそのまま渡しても問題はありませんが、のし袋や封筒に入れるとより丁寧な納め方になります。
ただ実際のところ、現金をそのまま渡すのは神様へのお供え物として少し失礼にあたるんですよね。日本の文化では、金銭を直接渡すことを避ける習慣がありますから。
日本では古来よりお金を裸のまま、現金のまま渡すことを避ける風習があり、結婚式や各お祝い、お葬式に至るまで多くの場面でお金をのし袋に包んで渡します。
ですので、初穂料も必ずのし袋か白い封筒に入れて準備するようにしましょうね。
「ふくさに包まずそのまま」はどうなの
こちらについては、のし袋をそのまま持参するのは避け、「ふくさ」に包んで持ち運び、渡す前にふくさから出すのが正式なマナーです。
ふくさはもともと金品を保護するためのものですが、現在では相手への敬意を表すための儀礼としても重要視されています。
とはいえ、「ふくさを持っていない!」という方も多いと思います。そんな時の対処法については後ほど詳しくお伝えしますので、安心してくださいね。
実際の神社ではどこまで許容されているか
正直なところ、のし袋に入れてなくても、現金を渡して受け取ってくれる神社・お寺もありますが、だからといって失礼していいわけではないんですよね。
神社側としては、やはり丁寧に準備されたものをいただく方が嬉しいはずです。
特に大きな神社や格式のある神社では、マナーをきちんと守ることが大切になってきますよ。
また、2025年の最近では、一部の神社でキャッシュレス決済を導入しているところもあるんです。
ただしこれは例外的なケースで、ほとんどの神社では従来通りののし袋で納めるスタイルが基本となっています。
初穂料の基本を知っておこう
初穂料について正しく理解しておくと、より心を込めてお供えできますよね。
基本的なことから確認していきましょう。
初穂料ってそもそも何のお金
初穂料は、神社でのご祈祷、お札やお守りを受けた際に納める謝礼金のことをいいます。
古くから農耕民族であった日本人は、春になると神様にその年の豊作をお祈りし、秋の収穫を迎えると神様への感謝と喜びを込めて、その年の最初に採れた稲穂である「初穂」をお供えしていました。
時代が変わって、その初穂の代わりにお金をお供えするようになったのが「初穂料」なんですね。
つまり、お買い物の「支払い」ではなく、神様への「感謝の気持ち」を形にしたものなんです。
玉串料との違いを簡単に説明
初穂料と似た言葉に「玉串料」というものがありますよね。これって何が違うんでしょうか。
初穂料は七五三やお宮参りなど、お祝いの場面で使用されることが一般的です。
一方、玉串料はお葬式や厄除けなど、より厳かな場面で使用されます。
簡単に言うと、初穂料は「慶事専用」、玉串料は「慶事にも弔事にも使える」という違いがあるんです。お祝い事の時は「初穂料」と書いておけば間違いありませんよ。
2025年の相場はいくら?シーン別に紹介
気になる金額の相場ですが、お子様1人に対して5,000円〜10,000円が目安となります。
シーン別に見ていきましょう。
| お宮参り | 5,000円〜10,000円が一般的です。初めてのお参りなので、5,000円から始める方が多いですね。 |
|---|---|
| 七五三 | こちらも5,000円〜10,000円程度。有名な神社では10,000円以上設定されているところもありますよ。 |
| 安産祈願 | 5,000円〜10,000円が相場です。安定期に入ってからの大切な祈願ですね。 |
| 厄払い | 5,000円〜10,000円が基本。厄年の方は少し多めに包む傾向もあります。 |
ちなみに、神社によってはごきょうだいで一緒に祈祷を受けると割引されるケースもありますので、事前に神社へ確認しておくと良いでしょう。
初穂料の正しい準備方法!のし袋の選び方から書き方まで
それでは、初穂料を準備する手順を見ていきましょう。
ポイントを押さえれば、そんなに難しくありませんよ。
のし袋はどこで買える?100均でもOK
のし袋は意外といろんなところで買えるんです。
- 100円ショップ(ダイソー、セリア、キャンドゥなど)
- 文房具店
- スーパーの文房具コーナー
- コンビニ
- ネット通販
100均のものでも全然問題ありませんよ。ただし、水引がプリントされているものより、しっかりした水引が付いているものの方が見栄えがいいですね。
10,000円以上なら水引付きの正式なのし袋、10,000円未満なら封筒タイプの簡易的なのし袋を選びましょう。
急いでいる方は、のし袋と筆ペンがセットになった商品も便利ですよ。書き方の見本付きのものもあって、初めての方でも安心して準備できるんです。
のし袋と筆ペンがセットになった商品も売っています。
(2026/02/01 03:46:22時点 楽天市場調べ-詳細)
急いでいる時や、書き方に自信がない方には見本付きのものもあって便利です。
100均でも買えますが、水引がしっかりしたものを選ぶなら、こういったセット商品がコスパもよくておすすめですね。
表書きと名前の書き方を画像で解説
のし袋の書き方、ちょっと緊張しますよね。でも基本さえ押さえれば大丈夫です。
表書きの書き方
- 水引の上:「御初穂料」または「初穂料」と書きます
- 水引の下:お子様のフルネームを書きます
名前の横にふりがなを振ると、神主の読み間違いを防ぐため安心です。
筆ペンか毛筆を使うのが正式なマナーですが、筆ペンの方が使いやすいのでおすすめですよ。
兄弟姉妹で一緒に参拝する場合は、右側から年齢の高い順に名前を並べて書きましょうね。
お札の入れ方と向きのポイント
お札の向きって意外と知らない方が多いんですよね。正しい入れ方を覚えておきましょう。
お札の向き
- お札の表面(人物がある方)を前に向けます
- 人物が上に来るように入れます
中袋への記入
- 表側:金額を縦書きで書きます(例:金五千円、金壱萬円)
- 裏側:お子様の名前と住所を書きます
お札は複数枚入れる時も、全て同じ向きに揃えて入れるのがマナーですよ。
新札じゃなくても大丈夫?きれいなお札の準備方法
初穂料は、神様への感謝を示すものですので、なるべく新札を用意するようにしましょう。
でも、「新札がどうしても用意できない!」という時もありますよね。
どうしても新札を用意できない場合は、なるべく折り目のついていない紙幣を選びましょう。汚れている紙幣や破れている紙幣は失礼にあたるので避けましょう。
新札の入手方法
- 銀行の窓口で両替
- 銀行のATMコーナーにある両替機
- 郵便局の窓口
土日祝日は窓口が休みなので、平日のうちに準備しておくと安心です。
もし当日になって「しまった!」という場合は、なるべくきれいなお札を選んで使いましょう。
ふくさの選び方と包み方|初めてでも簡単にできる
ふくさの準備、実は一度買っておけば長く使えるので、この機会に揃えておくのがおすすめですよ。
ふくさって本当に必要なの
ふくさを持っていないことに直前に気が付いたり、買いに行く時間が無い場合はどのように対応したらよいかと不安になる方も多いと思います。
でも、ふくさって本当に必要なんでしょうか。
初穂料はそのままバッグに入れるのではなく、ふくさと呼ばれる布の入れ物に収めてからバッグにしまうのがマナーです。
理由は2つあります。
- のし袋を守るため – バッグの中で水引が折れたり、のし袋がシワになるのを防ぎます
- 敬意を表すため – 相手への敬意や丁寧な気持ちを形で示すことができます
実際、ふくさに包んで持参する方と、そのままの方では、やっぱり印象が違うんですよね。特に格式のある神社では、きちんとした準備をしている方が安心して参拝できますよ。
どんな色やデザインを選べばいい
ふくさの色選び、迷いますよね。基本的なルールを知っておきましょう。
ふくさはその色柄によっても気持ちを表せます。お祝い事には暖色系のふくさを、お悔やみには寒色系のふくさを使うのが基本です。
慶事におすすめの色
- 赤、ピンク、オレンジなどの暖色系
- 紫色(慶弔両用なので一番おすすめ!)
紫色が便利な理由 紫のふくさなら慶事・弔事どちらにも使用できますので、これ一つ持っておけば安心なんです。
デザインは、シンプルで上品なものが使いやすいですよ。あまり派手な刺繍や柄が入っているものは、場面を選ぶこともあるので注意が必要ですね。
風呂敷タイプとポーチタイプ、どっちがおすすめ
ふくさには大きく分けて2つのタイプがあるんです。
風呂敷タイプ(包むタイプ) 正方形の1枚の布になっている風呂敷タイプのふくさは、のし袋を包む以外にもさまざまな用途で使うことができそうです。
メリット:
- 様々なサイズに対応できる
- 正式なマナーに沿った包み方ができる
- 畳めばコンパクトになる
デメリット:
- 包み方を覚える必要がある
- 慣れないと少し手間がかかる
金封タイプ(ポーチタイプ) 金封タイプとは、布でできた封筒のような状態になったふくさを指すようです。蓋を開いてのし袋などを挟み込むだけなので、包み方も簡単かもしれません。
メリット:
- 使い方が簡単
- 取り出しやすい
- 初心者でも扱いやすい
デメリット:
- サイズが限定される
- 豪華な水引がついたのし袋は入らないことも
私のおすすめは、初めての方なら金封タイプですね。使いやすさを考えると、金封タイプの方が当日慌てずに済みますよ。
包み方を確認しよう
風呂敷タイプのふくさを使う場合の包み方を見ていきましょう。
慶事の包み方(お祝い事)
- ふくさをひし形に置きます
- ひし形にした袱紗の上にのし袋を置きます
- 左側を内側に折ります
- 上側を下に折ります
- 下側を上に折ります
- 最後に右側を折って完成
ポイントは、「右開きになるように包む」ことなんです。これは「右側から開くことで、喜びが広がる」という意味があるんですよ。
弔事の時は左開きになるように包むので、慶事とは逆になるんですね。覚えておくと便利です。
私も最初はふくさなんて持っていなかったんですが、一つ買っておくと本当に便利なんですよね。
特に紫色のふくさは慶事にも弔事にも使えるので、これ一つあれば安心ですよ。
(2026/02/01 03:46:22時点 楽天市場調べ-詳細)
お値段も1,000円前後で買えるものが多いので、これを機に準備しておくのがおすすめです。
ふくさがない!そんな時の代用アイデア
「明日お参りなのに、ふくさを持っていない!」そんな時も慌てないでください。
代用方法がありますよ。
ハンカチで代用する方法
ふくさを持っていない場合でも、ハンカチなどを代用して使ったというママやパパの声がありました。
ふくさはもともと風呂敷のような1枚の布でできているので、ハンカチで代用することが出来ますんです。
ハンカチ代用のポイント
- 無地またはシンプルな柄のものを選ぶ
- 色は紺、紫、グレーなど落ち着いた色がおすすめ
- 大判のハンカチ(45cm×45cm程度)が使いやすい
- キャラクター柄や派手な色は避ける
色柄の決まりと包み方は風呂敷タイプと同様です。お祝い事・初穂料は右開きできるように包み、お悔やみの際は逆になるように包んでおきましょう。
「そんなハンカチ持ってない!」という場合は、次の方法もありますよ。
クリアファイルを使う裏技
ふくさを持っていない場合でも素手やポケットに入れたり、鞄に直入れするのではなくクリアファイルなどに入れておくのが無難でしょう。
クリアファイルなら、のし袋が折れたり汚れたりするのを防げますよね。もちろん、ふくさほど丁寧ではありませんが、そのままバッグに入れるよりはずっとマシです。
当日の朝に気づいた場合は、コンビニでクリアファイルを買って、その中に入れて持っていくのも一つの方法ですよ。
当日忘れた時の対処法
「家を出てから気づいた!」という最悪の場合でも、できることはあります。
- 近くの100均やコンビニで購入 – 神社の近くに店があれば、簡易的なものでも買っておく
- バッグの内ポケットで保護 – バッグの内側のポケットに入れて、できるだけ折れないように
- 正直に謝る – 受付で「ふくさを忘れてしまい申し訳ございません」と一言添える
神社の方も人間ですから、誠意を持って謝れば分かってくださいますよ。ただ、できれば前日までにしっかり準備しておくのが一番ですね。
神社での初穂料の渡し方|タイミングと言葉遣い
さて、準備ができたら次は当日の渡し方です。
ここでマナーを知っておくと、スムーズに進められますよ。
いつ渡すのが正解?受付での流れ
初穂料を渡すタイミングは、一般的に「祈祷前」と「祈祷後」のどちらかです。
初穂料の渡し方は、お宮参りの申し込みの時に渡すのが一般的。社務所で申込用紙を記入して、その際に一緒に渡します。
当日の流れ
- 神社に到着
- 社務所(受付)に行く
- 申込用紙を記入
- 申込用紙と一緒に初穂料を渡す
- 控室で待機
- 名前を呼ばれたら祈祷を受ける
ほとんどの神社がこの流れですが、念のため事前に確認しておくと安心ですね。
何て言って渡せばいい?おすすめのフレーズ
初穂料を渡すとき、何て言えばいいか迷いますよね。でも、難しく考える必要はありませんよ。
おすすめのフレーズ
- 「よろしくお願いいたします」
- 「初穂料です、お納めください」
- 「御初穂料をお渡しします」
- 「お供えください」
初穂料はお宮参りや七五三などで祈祷をしてもらう際に「神様への謝礼」としてお渡しするものです。神前にお供えするものなので、お渡しす際の言葉としては「お供えください」「お捧げいたします」などが適切と言えます。
丁寧に、でも自然な感じで渡せば大丈夫です。緊張しすぎないでくださいね。
ふくさから出すタイミングと渡し方
ここが一番気になるポイントかもしれませんね。正しい手順を見ていきましょう。
ふくさから出す正しい手順
- 受付の前でバッグからふくさを取り出す
- 自分側に正面を向けて左手の上に乗せ、右手でふくさを開いてご祝儀袋を取り出します
- ご祝儀袋を右回転させて相手から見て正面になるようにし、渡します
- ふくさは畳んで受付台の上においてもいいですし、畳んだふくさを台にしてご祝儀袋を上に乗せて差し出してもOKです
のし袋の文字を渡す相手に向くようにして両手で渡しましょう。
もし受付が混雑して人が並んでいるようなら、待っている間にふくさから取り出すところまでしておき、順番が来たら相手から見て正面になるよううにしてお渡しするのでも大丈夫です。
複数人で参拝する時の渡し方
兄弟姉妹で一緒に参拝する場合や、祖父母も同行する場合、誰が渡すべきか迷いますよね。
基本的な考え方
- お子様の名前で準備した初穂料は、ご両親のどちらかが渡す
- 複数のお子様分をまとめて渡してもOK
- 「2人分でお願いします」と一言添えると丁寧
祖父母が初穂料を負担してくださった場合でも、渡すのはご両親が行うのが一般的です。
シーン別|初穂料の渡し方で気をつけるポイント
それぞれの行事によって、ちょっとした違いがあるんです。
シーン別に見ていきましょう。
お宮参りでの初穂料マナー
お宮参りは赤ちゃんの初めての神社参拝ですよね。
お宮参り特有のポイント
- 赤ちゃんは父方の祖母が抱くのが伝統的ですが、最近は自由なスタイルも多い
- 初穂料は5,000円〜10,000円が相場
- 事前予約が必要な神社も多いので確認を
赤ちゃん連れで荷物も多いので、初穂料の準備は前日までに済ませておくと当日が楽ですよ。
七五三での初穂料マナー
七五三は11月が混雑するので、早めの準備が大切です。
七五三特有のポイント
- 兄弟姉妹で一緒に参拝する場合は人数分の初穂料を
- のし袋も人数分準備するか、連名で書く
- 神社によってはごきょうだいで一緒に祈祷を受けると割引されるケースもありますので、事前に神社へ確認しておくと良いでしょう
お子様が着物で動きにくいので、受付での手続きはスムーズに済ませたいですね。
厄払いでの初穂料マナー
厄払いは本人が参拝するので、大人のマナーとして丁寧に。
厄払い特有のポイント
- 初穂料は5,000円〜10,000円が基本
- のし袋の表書きは「御初穂料」または「御玉串料」
- 男性の場合、スーツで参拝される方も多い
厄年は人生の節目なので、心を込めてお参りしたいですね。
安産祈願での初穂料マナー
安産祈願は安定期に入ってから参拝します。
安産祈願特有のポイント
- 戌の日に参拝する方が多いが、体調優先で
- 初穂料は5,000円〜10,000円程度
- 腹帯を持参する場合は一緒にお祓いしていただく
妊娠中なので、無理のない範囲で参拝してくださいね。
2025年版|最新の初穂料事情
時代とともに、神社の対応も少しずつ変化しているんです。
2025年の最新情報をお届けしますね。
キャッシュレス決済に対応している神社も
実は最近、一部の大きな神社ではキャッシュレス決済を導入しているところが出てきたんです。
対応例
- QRコード決済(PayPay、LINE Payなど)
- クレジットカード決済
- 電子マネー
ただし、これはまだ限定的で、伝統を重んじる神社では従来通り現金・のし袋が基本です。訪問予定の神社のホームページで確認してみるといいですよ。
キャッシュレスに対応していても、正式な祈祷の場合は、やはりのし袋で準備する方が丁寧だと思います。
事前予約システムで当日がスムーズに
2025年現在、多くの神社がオンライン予約システムを導入しているんです。
予約システムのメリット
- 待ち時間が少ない
- 初穂料の金額が事前に分かる
- 必要な持ち物も確認できる
- 混雑を避けられる
特に七五三シーズン(11月)やお正月は混雑するので、事前予約がおすすめですよ。
コロナ後の変化したマナー
コロナ禍を経て、いくつかの変化もありました。
変化したポイント
- 社殿内の人数制限がある神社も
- マスク着用の可否は神社による
- 手水舎の作法が簡略化されているところも
- 初穂料の受け渡しも非接触を心がける神社が増加
基本的なマナーは変わりませんが、各神社の指示に従うことが大切ですね。
せっかくのお参りの機会、素敵な写真も残したいですよね。
最近は出張撮影サービスも人気で、神社での自然な表情を撮ってもらえるのが魅力なんです。
私の友人も利用していましたが、スタジオとは違った雰囲気の写真が残せて大満足と言っていました!
(2026/02/01 03:46:22時点 楽天市場調べ-詳細)
よくある質問|初穂料の渡し方Q&A
ここまで読んでいただいて、まだ疑問が残っている方もいるかもしれませんね。よくある質問にお答えしていきますよ。
Q1. のし袋は封をした方がいいですか
A. 中袋にはのりをせず、そのまま上袋に包んで納めましょう。本来、初穂料は「奉書紙」と呼ばれる和紙にお金を包んで納めていたため、のり付けする習慣はありませんでした。ですので、糊付けはしなくて大丈夫ですよ。
Q2. お寺で祈祷を受ける場合はどうすればいいですか
A. 神社とは異なり、お寺に七五三の祈祷を依頼する場合には、初穂料という表現は用いません。代わりに「祈祷料」や「御布施」としてお礼をお渡しします。のし袋の表書きも「御布施」と書いてくださいね。
Q3. 双子の場合、初穂料はどうすればいいですか
A. ごきょうだいがそろってご祈祷を受ける場合、初穂料は人数分を用意するのが基本です。例えば、初穂料が1万円でごきょうだいが2人の場合は、2万円を用意します。ただし、神社によって対応が異なるので、事前確認がおすすめです。
Q4. 初穂料を渡すときお釣りはもらえますか
A. 初穂料は神様へのお供え物なので、お釣りをお願いするのはマナー違反です。必ずぴったりの金額を準備してくださいね。
Q5. 受付で並んでいる時、先に袋から出しておいてもいいですか
A. もし受付が混雑して人が並んでいるようなら、待っている間にふくさから取り出すところまでしておき、順番が来たら相手から見て正面になるよううにしてお渡しするのでも大丈夫です。混雑している時は、むしろその方がスマーズですよ。
Q6. 初穂料の金額が決まっていない神社の場合、いくら包めばいいですか
A. 「お気持ちで」と言われた場合は、一般的な相場である5,000円〜10,000円を目安にしましょう。迷ったら5,000円が無難ですよ。
Q7. 厄払いの初穂料も慶事用ののし袋でいいですか
A. はい、厄払いは慶事として扱うので、紅白の蝶結びの水引ののし袋で大丈夫です。表書きは「御初穂料」または「御玉串料」と書いてくださいね。
[内部リンク:「冠婚葬祭の持ち物リスト」] 他にも忘れがちな持ち物をまとめていますので、お出かけ前にチェックしてみてください。
まとめ|初穂料は心を込めて丁寧に渡そう
ここまで、初穂料の「そのまま」に関する疑問から、正しい準備方法、渡し方まで詳しくお伝えしてきました。
- 初穂料は必ずのし袋か封筒に入れて準備する
- ふくさに包んで持参するのが正式なマナー
- ふくさがない時はハンカチやクリアファイルで代用可能
- 受付で申込用紙と一緒に渡すのが一般的
- 相手から見て正面になるように、両手で丁寧に渡す
- 2025年は一部キャッシュレス対応の神社もあるが基本は現金
初穂料は単なるお金の支払いではなく、神様への感謝の気持ちを形にしたものなんです。
だからこそ、丁寧に準備して、心を込めて渡すことが大切なんですよね。
初めての時は不安も多いと思いますが、基本的なマナーを押さえておけば大丈夫。あとは感謝の気持ちを持って、お子様やご自身の健やかな成長を願う、その気持ちが一番大切ですよ。
素敵なお参りになりますように。