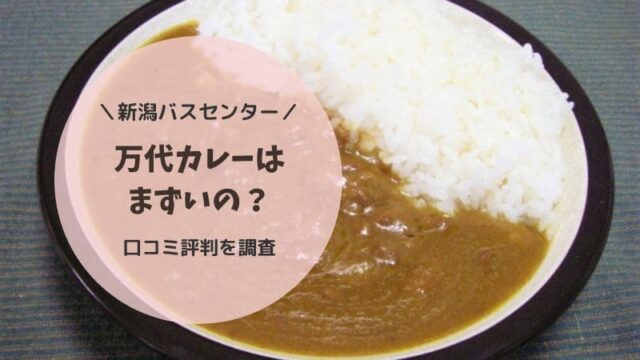スーパーや居酒屋で「いわし」と「さんま」が並んでいると、どちらを選ぶか迷った経験はありませんか?
見た目が似ていて同じ青魚に分類されるため「味や栄養もほとんど同じでは?」と思う人もいるはずです。
しかし実際には、旬の時期や脂ののり方、栄養面などで意外な違いがあります。
この記事では「いわし」と「さんま」の違いをわかりやすく比較しながら、味の似ている点と異なる点を徹底解説します。
いわしとさんまはどう違うのか一目でわかる比較
まずは全体像を押さえるために、いわしとさんまを表で比較してみましょう。
見た目や味、栄養、旬の時期などを整理すると、パッと違いが理解できます。
| 項目 | いわし | さんま |
|---|---|---|
| 見た目 | 体長15〜20cmほど、丸みがあり小ぶり。背は青緑色。 | 体長30cm前後、細長く刀のような形。背は青黒色。 |
| 味の特徴 | 身がやわらかく脂が多い。煮付けやフライ向き。 | 脂がのって香ばしい。塩焼きや刺身向き。 |
| 栄養 | DHA・EPA豊富、カルシウムも多い。骨ごと食べるとさらに◎ | DHA・EPA豊富。ビタミンB群や鉄分も含む。 |
| 旬の時期 | 初夏(5〜7月)、秋(9〜11月)に脂がのる | 秋(9〜11月)が最盛期。まさに「秋の味覚」 |
| 主な産地 | 千葉・長崎・宮城など全国広く漁獲 | 北海道・三陸沖・根室など北日本中心 |
| 価格帯 | 比較的安価。庶民の魚の代表格 | 近年は不漁で高騰気味。特に旬の秋は高値になることも |
| 食文化 | 「いわしの節分」など行事食あり | 秋の風物詩。「目黒のさんま」など文学作品にも登場 |
| 味の似ている点 | 青魚特有の旨みと脂を楽しめる点は共通 | 同じ青魚なので香りや脂の印象が似ていると言われる |
この表を見ると「やっぱり似てる部分も多いけれど、違いもはっきりある」と気づけるはずです。
いわしとさんまは本当に味が似ているのか
「いわしもさんまも、食べると味が似てる」と感じる人は少なくありません。
確かにどちらも青魚特有の脂の旨みがあり、焼くと香ばしい匂いが立ち上ります。
しかし実際に食べ比べると、微妙な違いが感じられます。
料理別で比べてみると
塩焼きで比べると、さんまは香ばしさと脂の甘みが強く、秋の風物詩として親しまれています。
一方、いわしは小ぶりで脂がにじみやすく、焼き上がりがジューシー。
脂質が多いため、人によっては「いわしの方が重たく感じる」こともあります。
煮付けでは、いわしは身がやわらかいので甘辛いタレが染み込みやすく、骨まで食べやすいのが特徴です。
さんまの煮付けは香りが強く、苦味のあるワタ(内臓)を一緒に煮ることで大人の味わいになります。
刺身で比べると、新鮮ないわしはとろけるような旨みがあり、さんまはさっぱりしつつもコクがある。
秋にしか味わえない特別感もあり、同じ「青魚の刺身」でも印象が違います。
好みが分かれるポイント
「脂がしっかりある方が好き」ならいわし寄り。
「香ばしくてキレのある味」ならさんま寄り、と好みが分かれることが多いです。
確かに味は似ていますが、じっくり味わうと違いがはっきりわかるでしょう。
旬の時期と産地の違い
旬を迎える季節も微妙にずれています。
いわしは初夏(5〜7月)と秋(9〜11月)の二度が旬とされ、特に脂がのる時期は美味しさが際立ちます。
産地も広く、千葉や長崎、宮城など全国各地で水揚げされています。
一方、さんまの旬は秋の9〜11月で、北海道や三陸沖で獲れるさんまは脂がのって絶品。
スーパーの鮮魚コーナーにさんまが並ぶと「秋が来たな」と感じる人も多いはずです。
値段や入手しやすさの違い
いわしは比較的安価で、庶民の味方として長年親しまれてきました。
缶詰や加工品でも広く流通しており、日常的に手に入りやすい魚です。
さんまは以前は安価で秋になると1尾100円以下で買える庶民の魚でしたが、近年は不漁が続き、500円以上になることも増えてきました。
特に旬の秋には「高級魚」と呼ばれることもあり、ニュースで取り上げられるほど価格が変動しています。
🧐🐟
「サンマ」はもはや高級魚!? 10年で価格は「3倍以上」に! 価格高騰の原因も解説#Yahooニュースhttps://t.co/SguGGDUFks— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) October 15, 2023
健康効果と食卓での使い分け
どちらも青魚らしくDHAやEPAといった不飽和脂肪酸が豊富で、動脈硬化や生活習慣病の予防に効果が期待できます。
いわしはカルシウムが豊富で、小魚なので骨ごと食べやすいのがメリット。
成長期の子どもや骨粗しょう症予防が必要な高齢者には特におすすめです。
さんまは鉄分やビタミンB群を多く含み、貧血予防や疲労回復に役立ちます。
秋の旬に脂がのったさんまを食べると、季節の変化で落ちやすい体調を整える効果も期待できます。
居酒屋・雑学ネタで役立ついわしとさんまの豆知識
名前の由来にも面白い違いがあります。
いわしは「弱し(よわし)」が語源とされ、鮮度が落ちやすい魚だからといわれています。
さんまは「狭真魚(さまな)」が転じたもので、細長い体型を表した名前だと言われます。
文化的にも両者は日本人の生活に深く根付いてきました。
いわしは節分に「焼きいわし」を飾って鬼を追い払う風習があります。
さんまは落語「目黒のさんま」に登場し、文学作品や映画の題材にもなるほど。
こうした豆知識を知っていると、居酒屋や食卓での会話が弾む小ネタになります。
「いわし」と「さんま」の違いまとめ
「いわし」と「さんま」は同じ青魚で味が似ている部分もありますが、見た目や旬、栄養、文化的な背景まで多くの違いがあります。
いわしは安価で骨ごと食べやすく、カルシウムが豊富。
さんまは秋の旬に脂がのり、塩焼きにすると香ばしい味わいが楽しめます。
迷ったときは「子どもや高齢者にはいわし」「秋のごちそうにはさんま」と覚えておくと、食卓での使い分けがしやすいですよ。
▼こちらの記事もどうぞ▼
さんまを美味しく保存するコツ!冷蔵・冷凍・そのまま保存まで徹底解説